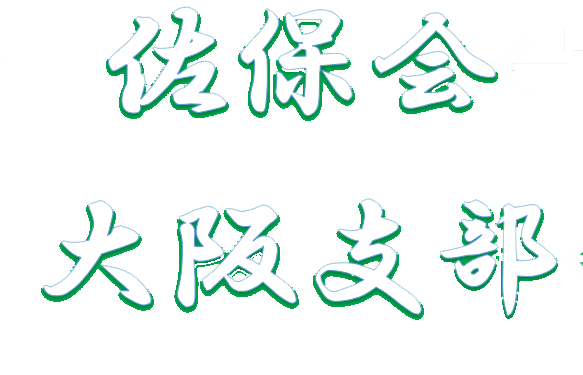~ 箏曲の世界へ ~

1.四季のわらべうた (古謡)
貴調会 編曲
古くから親しまれているわらべうたのメドレー
(さくらさくら・ほたるこい・うさぎうさぎ・かぞえうた)

2.六段の調べ (江戸時代)
八橋検校 作曲
箏曲の開祖・八橋検校の原点ともいえる器楽の名曲 同じ拍数の六つの「段」で構成されている
「六段の調べ」の作曲者、八橋検校は、江戸時代初期の方ですが、それまでの雅楽の伴奏楽器だった箏を、「箏曲」として独自のジャンルの音楽に発展させました。八橋検校を偲び、箏の形に仕上げたお菓子、堅焼き煎餅が、京都の銘菓「八つ橋」です。 江戸時代に売り出され、大流行したそうです。

3.時鳥の曲 (明治時代)
楯山 登 作曲
古今和歌集の中のホトトギスを詠んだ歌と、
明るく華やかな旋律で初夏の風景を描いた明治新曲
後半に出てくるホトトギスの鳴き声を表した部分が面白い
「箏曲」、箏は地歌の三味線音楽と共に発展したので、実は多くの曲に歌詞があり、弾きながら歌います。

4.銀嶺 (平成)
佐藤義久 作曲
うっすらと雪化粧した遠い山並み、真っ青な空、ひんやりとした空気
そうした清々しい遠景をダイナミックに描いている
昭和に入ってからは、箏曲に西洋音楽を取り入れたり、他の和楽器や洋楽器との合奏など、多様な音楽が生まれました。

5.ミレニアムロード (平成)
水野利彦 作曲
2000年に作曲されたこの曲は、「若々しさ」「躍動感」
そして「新世紀への希望」をテーマに
若者がそれぞれの人生を歩む姿を描いている


17絃
17絃は、「春の海」の作曲で有名な宮城道雄が、より多彩な表現を求めて大正10年に考案しました。上の合奏の写真では、左と真ん中が一般的な13本の絃の箏、右は絃が17本ある17絃です。17絃は箏よりも低い音を出すことができます。

楽譜について
上から 「一 五 三 一二」実はこれは、先ほどの「六段の調べ」の楽譜の一部です。 箏 の楽譜は、一般的に現在も、このように漢数字を使います。一 は、引き手から一番遠い 一絃 を弾く。 五 は 5番目、三 は3番目の絃です。一二 二つ並んでいるのは 1絃と2絃を両方弾きます。 一から十番目までが、漢数字。13本の絃がありますので、11、12、13番目は、 斗、為、巾 と漢字を当てます。

~歌って 楽しく~
6.夏は来ぬ 日本の唱歌 佐々木信綱 作詞 小山作之助 作曲
7.バラが咲いた フォークソング 浜口庫之助 作詞・作曲
8.奈良女子高等師範学校校歌
御歌 貞明皇后御下賜 作曲 東京音楽学校
箏の伴奏で合唱して楽しみました。
懐かしくて心が和む音。それでいて力強い魅力ある演奏でした。
奈良女子大学箏曲部飛鳥会 第70回定期演奏会のご案内
飛鳥会部長の川村さんよりお知らせ。
日時:2023年10月7日(土)
開演:午後1時半
会場:奈良女子大学講堂
花束贈呈
加地支部長より、お礼の花束贈呈
貴調会
奈良女子大学箏曲部を指導された故井上令節先生の門下生のグループ
現在、菊領令華先生が代表

飛鳥会
奈良女子大学箏曲部 定期演奏会のほか、ミニコンサート、地域のイベントにも出演